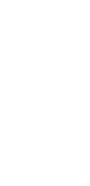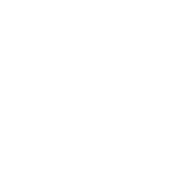お知らせ
〜小堀杏奴のおはなし 01〜
「パッパ、手」
そういって私は父の差出す手を両手で大切そうに持って寝た。手を持っていると、安心してよく寝られるような気がした。
「パッパ、僕にも手」
どうかすると両方から、片方ずつ手を貰って持って寝た。そうして何時の間にか、私は知らない中に眠ってしまった。

小堀杏奴(1909-1998)は、昭和から平成にかけて活躍した随筆家・小説家です。小説家、随筆家、そして軍医として知られる森鷗外の次女として生まれ、13歳という多感な時期に父親の死を経験しました。これは、小堀杏奴の代表作『晩年の父』で描かれた鷗外と弟の類との様子です。娘ならではの視点で、鷗外の穏やかで優しい父親としての表情が詳細に描かれています。

鴎外は杏奴のことは、パッパの子供のかわいいアンヌコという意味で「パッパコアンヌコ」、坊ちゃんと呼ばれていた弟の類のことは「パッパコボンチコ」と、自分と子供たちだけで分かる面白い名前を用いるなど、子供たちとの時間をとても大切にしていました。また、鷗外は死期が迫った晩年も、杏奴の女学校への試験準備のために自分が働く役所へ連れて行って数学を勉強させたり、歴史や地理の本を分かりやすく抜書したりするなど、少しでもアンヌを育てよう、助けようとしていた様子が分かります。


女学校卒業した杏奴は、類とともに画家藤島武二に師事し、昭和6年(1931年)フランスに渡ってパリで洋画を学びました。帰国後は、油彩画家である小堀四郎(1902-1998年)と結婚。小堀四郎も藤島武二に師事し、フランスに留学していました。松田改組によって美術界が混乱する中、恩師・藤島武二の助言で、生涯画壇に属さず、画商と交渉せず、東京美術学校同期生による「上杜会」のみに出品するという、独自の芸術の道を歩み続けました。そんな四郎を生涯にわたって理解し、支え続けたのが杏奴でした。

小堀夫妻には二人の子供がいました。長男の鷗一郎氏(1938〜)は鴎外と同じく医療の道に進み、東大附属病院第一外科で、食道がん専門の外科医として活躍。定年後は在宅医療に携わり、そこでの看取りの経験を綴った『死を生きた人びと:訪問診療医と355人の患者』を執筆しました。
小堀一家が蓼科を訪れたのは昭和20年(1945年)のことで疎開のためでした。蓼科 親湯温泉の現在の社長である幸輝が直接鷗一郎氏に聞いた話によると、当時、蓼科に別荘を持っていた東京パンの社長が疎開するから大切なものを蓼科で預かろうと四郎に伝えたところ、四郎は金目のものではなく、自身が描いた絵画を山ほど託したといいます。これをきっかけに四郎は疎開を一週間で決意し、東京パンの社長が勧めた蓼科で別荘を購入しました。

このとき別荘の手配など、蓼科での暮らしをサポートしたのが、蓼科 親湯温泉(当時は三幸旅館)の二代目社長である柳沢幸男でした。以来、小堀家と柳沢家は家族ぐるみの付き合いを行っていました。そのつながりの深さを物語るように、蓼科 親湯温泉には、四郎から寄贈された絵画が何点も残り、鷗一郎氏と現社長との交流もまた続いています。